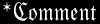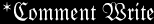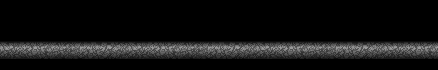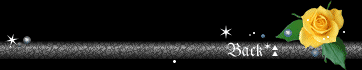透也先輩、と話してた、です。
修学旅行、どんなものか教えてもらった、です。
楽しそうです、と言ったら、お土産を買ってくると、言ってくれました。
ほんのり、胸があったかくなった、です(頷)
それから、不意に思い出したみたい、にレイン先輩の、誕生日が明日なのも、教えてくれた、です。
誕生日、生まれた日。
小唄にはその程度の認識しかない。
喜ぶべき日である、その認識がない。
気が付けば過ぎている日、その程度。
今一緒に暮らしている、現保護者とでも言うべき人物に聞いてみようと思ったのは大いなる進歩であろう。
「誕生日ってどんなもの、ですか」
「珍しいな、小唄がそういうの聞くのは」
くすりと笑って言う男の名前は月読・狼(つくよみ・ろう)。
年齢不詳、性別男、正体不明。
あの日、小唄に名前をくれた男がいなくなって、どうすればいいのか廃屋で途方に暮れていた小唄を拾った稀少な男だ。
「俺は何もする事がなくなったから暇なんだ。お前が望むなら養ってやる、一緒にくるか選べばいい」
今でも小唄が覚えている、その言葉。
望んだのかは今でもわからないけれど、小唄はその手を取ったのだ。だからここに、こうして生きている。
「どんなもの、ですか」
もう一度、問う。狼が読みかけの本を閉じて答える。
「小唄が、その人を好きならばその人が生まれてきた事を喜び、祝う日」
「喜び、祝う、日・・・」
「小唄はその人が好きなのかい?」
「・・・好き、っていうのまだ、わからない、です。でも、その人の、笑った顔見ると、あったかくなる、です」
たどたどしく喋る小唄の言葉を聞いて、ふっと笑う。
「それは好きって事だよ、小唄。何かしてあげたい、したいって思ったんだろう?」
「狼は何でも、知ってる、です」
こくこくと頷いて小唄が無表情に顔を上げる。
頷いた小唄の頭をぽんと撫でて狼が立ち上がって席を外す、程なくして戻ってきて小唄に少し大きめの箱を渡した。
中には色とりどりのクリスタル、ビーズが入っていた。
「それ、女の子だろう?前に言っていたレイン先輩っていう。その人に似合いそうな色のを小唄が選んでごらん」
「・・・狼は本当に、なんでも知ってる、です」
不思議そうに首を傾げながらも言われたとおりに選んでいく。
言われるままに、ゴムテグスの糸に通してゆく。
無表情なのに、一生懸命に作業をしている小唄を微笑ましく思いながら狼は見ていた。
完成したモノにを、狼が手伝いながらラッピングをして。
メッセージカードも添えて。
翌日--------------------------------------------------------
「・・・喜んで、くれる、ですか?」
「気持ちが伝われば、きっとね」
手の中の小さな包みを渡した時、小唄の世界はもう少し広がるだろうと確信しながら狼はその背中を押して見送った。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
帰ってきた小唄を、優しく迎え入れる。
「どうだった?」
「はい、喜んで・・・・くれた、です」
その顔は、目は未だ表情についてきてはいなかったけれど、唇が少しだけ微笑む形になっていて。
狼は破顔して喜んだ。
PR