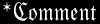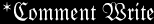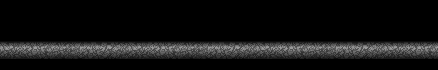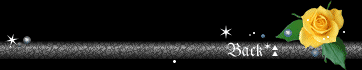先日、七夕のお祭り行った、です。
狼が、一人ではダメ、と言う、です。
「お友達を誘いなさい」
・・・難しい事、言われた、です。
お友達・・・お友達?お話、する人は、いっぱいできた、です。
でも、お友達・・・勝手に思ってもいい、ですか?
たくさん、悩んで、よくGTに一緒、してもらう先輩、誘ってみた、です。
そうしたら、いいよ、と言ってくれた、です。
嬉しい、です(ほんのり、口の端が上がってるようだ)
狼が、小唄に浴衣を着せて綺麗に髪まで結い上げる。
高く結い上げられた髪に髪飾りをつけて、薄く紅を引いて小唄を鏡の前に立たせる。
「うん、可愛くできたよ。小唄に似合うと思って一通り揃えてよかった」
満足気に狼が笑う。
「ありがとう、です、狼」
和装は慣れているから動くのは辛くない。
「では、いってらっしゃい。一緒に行ってくれる先輩に、保護者がよろしくお願いしますって言ってたと伝えておくれ。帰ってきたらケーキを一緒に食べよう、小唄」
楽しそうに笑う狼に見送られて、家を出る。カランコロン、と下駄を鳴らして巾着を揺らしながら餐場と待ち合わせた場所まで歩いてゆく。
距離はそう遠くない、15分も歩けば着くぐらいだ。
待ち合わせ場所に着くと、そこには紺地に水色の波柄の浴衣をすらりと着こなして餐場が立っていた。
「お待たせ、です」
「大丈夫、待ってない」
行こうか、と促されるままに電車での移動になる。少し時間はかかるけれどその間に七夕とはどういうものか聞いたり、修学旅行の話を聞いたりしている内に目的地に着く。
「迷子、なるといけない、から」
そういって繋いだ手は少しひんやりとしていて気持ちいい、小唄はこくりと頷いてきゅっと握り返す。
カランコロン、と涼しげに下駄の音が響く、小唄や餐場の他にも七夕のお祭りを堪能しにきている者が沢山いた。色々見て回って、少し疲れた頃に六角堂手前に辿り着く。
「アイス、食べる、かい?」
薄っすらと汗ばんでいる小唄を思ってか餐場がそう提案する。
「アイス・・・!食べる、です」
無表情ながらに、声のトーンが少し上がったのを餐場が静かに笑いながら二つアイスを買い、片方を小唄に渡す。手に心地いい冷たさを感じながら六角堂まで移動して腰を落ち着ける。
「おいしい、です」
どうしたら嬉しいのや楽しいのを伝えられるだろうか、お兄ちゃん、というのはわからないけれど、もしもいたらこんな感じなのだろうか。小唄は少しでも伝えてみたくて最近覚えた笑顔――というには程遠いが唇の端を少し持ち上げてみる。
「小唄が、楽しいのなら、何よりだ。俺も、嬉しい」
そういって、餐場が小唄の頭を優しく撫でた。
撫でられるのは嬉しい、狼とはまた違う優しい手。
「あ、そうだ。これ――」
小さな包みを取り出して、餐場が小唄に渡す。
不思議そうな顔をして、小唄が受け取ると、
「誕生日、おめでとう。これから、もっと、色々表せるようになればいい、な」
小唄が目を丸くする、そういえば誕生日だったのだ。祝ってもらった事などなかったから、ひどく吃驚する。出掛けに、狼がケーキを食べようと言っていたのはそのせいだと気がつく。
包み紙を開けて中を見る、小さな紫金石のはめられたイヤリングだ。少しだけ手間取りながらもイヤリングを身に付ける。
風をうけて僅かにイヤリングが揺れた。
「ありがとう、です・・・!」
今度は、確かにはっきりと唇が笑みを作る。
それを受けて、餐場も微笑んだ。
家に帰ったらケーキを食べながら狼に話そう、今日の嬉しかった事を。
こうやって少しずつ時間をかけてひとつひとつを覚えていく。
毎日が宝物のようだ、と小唄は思う。
あの日の惨劇は忘れられるモノではないけれど、忘れるつもりもないけれど。
真っ白な自分に新しい色が増えてゆく事を恐れない、どんな色でも受け止める。
嬉しい事。
怒る事。
哀しい事。
楽しい事。
少しずつでは、あるけれども。
PR